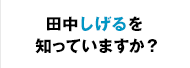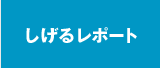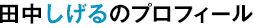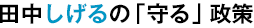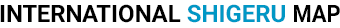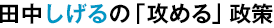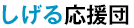最近のことですが、ある広報誌から依頼を受け自らの心境として「永遠の今」という一文を奏しました。
「永遠の今」とは、第68代総理大臣に就任した大平正芳先生(1910~1981)が座右の銘とした言葉でした。
その意味を先生は次のように述べられていました。
「現在というものは、未来を指向する力と過去の持つ引力という、相反した方向に働く二つの力の緊張した相克の中にある。そして時間は、いつも現在という衣を着けてわれわれを訪れるものである以上、現在は永遠であり、襟を正して立ち向かわなければならないものである」
釈迦は人間が持つ苦を「生老病死(しょうろうびょうし)」としました。考えてみれば、古今東西の文学作品はすべてこの4つの苦をテーマにしているといっても過言ではないでしょう。そして、これらの苦は「生」から始まるもので、そこに内包されているものです。つまり、苦とは人間の存在自体が抱えた問題なのであり、それを抱え与えられた命をどう生きるか、全うするか、それが永遠の問題なのです。
時間は日本人的に言えば「行く川のように絶えず流れて」いきます。もしくは永遠に続く小さな点の連続として考えることができます。普段、私たちは時間について大きな流れとしてみていることが多いように思います。ところが実際には、いわば「一瞬の点の集合」でできていて、確実なのは今の一瞬に生きているだけで、その次の瞬間は何が起こるかわかりませんし、また過ぎた瞬間は永遠に取り戻すことができません。
私は次のように書きました。
~人間に与えられた時間は常に今しかありません。過去はすでになく、未來は未だ存在していません。今の一瞬をどう生きるかが、すべてなのです。
中曽根康弘元総理の造語に「結縁・尊縁・随縁」があります。私自身はこれまで、先生から学んだこの三つの縁を大切にして生きてきました。その意味は、人は一人で生きているものではなく、人と一度縁を結べば、その縁を大切にして、その縁に随って生きなさい、ということです。
禅語に「生死事大 光陰可惜 無常迅速 時不待人(しょうじじだい こういんおしむべし むじょうじんそく ときひとをまたず)」という言葉があります。意訳すれば、「生まれて死ぬことが定められた人生をいかに生きるか、それが大事である。時は矢のように過ぎ去る。無常ではないものがあるだろうか」ということです。この世に常に存在するものはなく、人生にも限りがあり、時間はあっという間に過ぎてしまいます。
~今の一瞬を、過去も未来も含んだ永遠として生きる。これこそ仏教の悟りの境地と言えるかもしれません。人との縁を大切に、一瞬を大事に生きる努力を続けていきたいと思っています。
<哲学のない時代>
現代は哲学のない時代、言い換えれば物事の本質を考えようとしない時代といえるでしょう。それは、1960年前後から始まった、高度経済成長がもたらした物質主義の日本人的な受け入れ方の結果といえるかもしれませんし、また、戦後一貫して行われてきた詰め込み教育偏重の結果といえるかもしれません。
戦前の旧制高校では、哲学を学ぶことはごく当たり前のことでした。それは学生たちに愛唱された「デカンショ節」にも表れています。学生たちにとっての「デカンショ」とはデカルト、カント、ショーペンハウエルという哲学者達の名前を一つにしたものでした。「デカンショ、デカンショで半年暮らす アヨイヨイ あとの半年ねて暮らす ヨーオイ ヨーオイ デッカンショ」というものですが、ことほどさように旧制高校時代の学生にとって、哲学書を読み、学ぶことはごく日常的なことでした。
しかし、戦後の教育では長いこと哲学は無視されてきました。その代りに重視されたのが詰め込み式の覚える教育でした。基本的な事柄を暗記し知識量を増やすことは、人間の学習過程で非常に重要なことで、若いうちに知識を覚える習慣を身につけることは必要です。世界に追いつけと豊かさを求めた高度経済成長の時代に、物事の本質を考えるような教育をするより、そのほうが手っ取り早く、人材の育成にも役立ったのでしょう。戦後のベビーブーム時代から続いた生徒数の多さもそれに輪をかけました。一つの年度に生徒数が50人というクラスが9つも10もあるような学校で、生徒一人ひとりの個性を活かした教育を行える余裕がなかったのでしょう。受験勉強では「デカンショ」が書いた哲学書は読まなくても、「デカンショ」が何者であり、その著作物のタイトルを知っていれば問題はなく、それが教養として認められたのです。
小川仁志・山口大学国際総合科学部准教授は、『日本のエリートに欠ける「本質」見抜く力の源』(東洋経済オンライン)の中で、めまぐるしく変わる時代を切り開こうとするなら、これまでとは違った能力を身につける必要があると説きます。そして、それを「混沌とした時代を分析する力」「正解がない中で決断する力」「難問を解決する力」「新しい価値を生み出す力」とし、その思考力を形づくるベースを「教養=リベラルアーツ」としています。教養といっても覚えるものではなく、本質を理解する力を養う教養といえます。
多様化の時代にあっては、正解は必ずしも一つに限るわけではありません。
日本人の中でも考え方は決して一つではありません。民族が違えばアイデンティティも違い、当然考え方も違います。その違いを理解するのには、まず自らの考えを明確にすることが求められます。そうでなければ相手との考えの違いを理解することは難しく、共存することも難しいでしょう。
欧米ではリベラルアーツを学ぶことがごく普通のことです。私がアメリカの大学で学んだのは40年も前の話ですが、一番苦労したのが与えられた分厚い原書を読んで理解することでした。日本とまったく違っていたのは、与えられたテーマについて考えさせ、自分で答えを出させる点でした。たとえば第2次世界大戦は何故起きたのか、なぜこのような結果になったのかを自分で調べて、自分なりの答えを導き出さなければいけないのです。暗記とは違い、ものの本質がどこにあるかをたぐらせるのです。どのような問題でも、その本質は何で、それはどこにあるのかを考える教育を受けました。
フランスのトップ官僚や政治家を輩出する国立行政学院(ENA)の校長を務め、現マクロン政権で欧州問題担当大臣を務めるナタリー・ロワゾー女史は、「エリートが教養豊かな知識人でなければならないという価値観は、フランスの伝統そのものです。事実、ENAの入試では、一般教養の知識をかなり問います。リーダーになるためには、高度な常識が絶対に必要だからです。中世の詩を暗唱したり、ルネサンス期の音楽家について問いたりするような知識ではありません。世の中の出来事を哲学的、文化的、歴史的な観点から検証する能力です。つまり、『出来事の背景にある価値観を見抜く高度な常識』が問われ、今必要なのは将来を予測し未来に備えることです」と言っています。リーダーの素養としてのリベラルアーツが重要視されている証拠といえるでしょう。
以前書きましたように、国の進路を決めていく政治家や官僚にとって必要なものは、ノブレス・オブリージュの精神や、ナタリー・ロワゾー女史が指摘する本質を見抜く力(高度な常識)ではないでしょうか。
9月20日に行われる自民党総裁選は、安倍晋三総理と石破茂元幹事長の戦いといわれていますが、下馬評では安倍総理の3選は間違いないといわれています。自民党の総裁に選ばれることは現在、総理になることですから、安倍総理が当選すれば、次の3年間も政権を担当することになります。都合9年という歴代総理の中で最も長い期間を務めることになります。
立候補するいずれの候補が勝つにせよ、この3年は日本の命運を決めるといっても過言ではないほど、重要な行事や政治日程が目白押しです。また経済環境も厳しくなることが予想されています。前述した小川仁志准教授の掲げる「混沌とした時代を分析する力」「正解がない中で決断する力」「難問を解決する力」「新しい価値を生み出す力」をぜひ発揮していただきたいと思います。
最後に中曽根康弘元総理と哲学の関係を述べておきたいと思います。中曽根元総理は、旧制静岡高校から東京帝国大学へ進学した、いわば「デカンショ」世代でもあります。学生のころはパスカルの『パンセ』の翻訳を半ばまで手がけたとうかがいました。
これまでの自らの行動を律してきたものとしてカントの哲学をあげ、次のように記しています。
~繰り返し、じっと反省すればするほど常にそして高まりくる感嘆と崇高の念をもって心を満たすものが二つある。わが上なる星の輝く空とわが内なる道徳律とである。
若き日の私は、このカントの教えに沿って生きてきたといえるかもしれない。それは私が立派な人格を備えていたという意味ではない。誰にでも自らの行動を律するとき、わが内なる道徳律が存在し、私もそれに従って行動してきたにすぎないということである。
『日本人に言っておきたいこと』(PHP研究所)